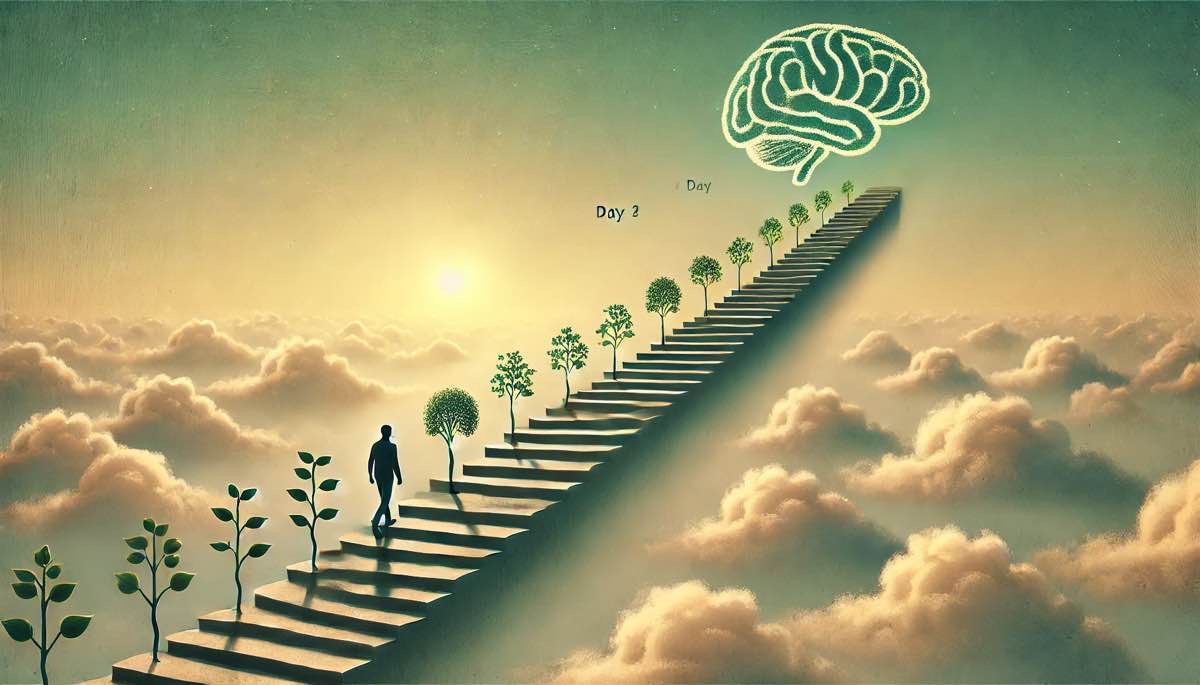「思考って、どうやったら変えられるの?」
ポジティブに考えたいのに気づけばネガティブ…。そんな自分にモヤモヤして、「よし!思考を変えてみよう」と決意しても、続かない人ってすごく多いんです。
でも、実は“思考の習慣化”にはちょっとしたコツと、必要な「期間」があるって知ってますか?
この記事では、「思考の習慣化ってどれくらい時間がかかるの?」「途中で挫折しない方法は?」といった疑問に答えながら、誰でも実践できるステップを紹介していきます。
続けられないのは、あなたの意志が弱いからじゃない。
“脳のクセ”をうまく味方にすれば、ちゃんと「考え方」は変えられるはずです。
習慣化に必要な平均日数はどれくらい?
66日が目安って本当?ロンドン大学の研究から解説
習慣化に必要な日数の目安としてよく言われるのが「66日」という数字。
これは、ロンドン大学のフィリッパ・ラリー博士の研究が元になっています。
博士が行った実験では、96人の被験者がそれぞれ新しい行動(たとえば「昼食時に水を飲む」「夕食前に15分間走る」など)を12週間続けて、どのくらいで自動的な習慣になるかを調査。
その結果、平均して「66日」で習慣化できたことがわかりました。
でも実際には、18日でできた人もいれば、254日かかった人もいて、けっこう幅があります。
この「66日」はあくまでも“平均値”だから、絶対にみんなが66日で習慣化できるわけじゃないってことを覚えておきましょう。
続いて、特に「思考」の習慣化がどうしてそんなに時間がかかるのかも見ていきます。
思考習慣は6ヶ月かかる理由とは?他の習慣との違いも紹介
行動習慣や生活習慣と比べて、思考を変えるのってすごくむずかしい。
その理由はズバリ、「思考は無意識のクセとして長年染みついてる」から。
たとえば、「ポジティブに考える」とか「完璧主義をやめる」って、いきなり明日から変えられるものじゃないですよね。
この“思考の習慣化”には、なんと約6ヶ月かかるって言われています。
他にもこんな違いがあります。
| 習慣の種類 | 例 | 習得までの目安 |
|---|---|---|
| ごく簡単な行動 | 歯磨き、手洗い | 約18日 |
| 行動習慣 | 日記、読書、片づけ | 約1ヶ月 |
| 身体のリズム習慣 | 運動、早起き、禁煙 | 約3ヶ月 |
| 思考習慣 | ポジティブ思考、完璧主義の脱却 | 約6ヶ月 |
つまり、思考を変える=自分の価値観や無意識のクセに向き合う作業だから、時間も根気も必要ってこと。
「全然変わらない…」って途中で投げ出す人も多いけど、6ヶ月くらいかかるって最初から知っておくだけでも、気持ちが楽になります。
次は、その「習慣化の過程」でぶつかりやすい3つの壁について詳しく紹介していきます。
習慣化の「3つの壁」とは?失敗しやすい時期に注意
第1段階「反発期」は最初のやる気が消えるタイミング
思考の習慣化を始めたばかりの頃にやってくるのが「反発期」。
この時期は、頭では「やらなきゃ」って思ってても、なぜか行動が続かない…そんなモヤモヤを感じやすいんです。
この反発期は思考習慣の場合、始めの約45日間が該当すると言われていて、実際にここで挫折しちゃう人が42%もいます。
「やっぱり自分には無理かも…」って思うのもこのタイミング。
でも大丈夫。
この時期は“とにかく続ける”ことが大事だから、毎日1ミリでも意識できたらOKって考えてください。
「今日はちょっとだけでも前向きに考えられた!」っていう小さな成功体験を大事にしよう。
第2段階「不安定期」は習慣のリズムが崩れやすい
反発期をなんとか乗り越えて、「ちょっと慣れてきたかも〜!」って感じる頃にくるのが、不安定期。
思考習慣ではだいたい46日〜135日目くらいがこの時期になります。
ここでは、日によって気分にムラが出たり、ちょっとした予定変更でリズムが崩れて、「あれ、またネガティブになってる…」なんてことが増えやすい。
でもこれは“自分の癖がまだ根っこにある証拠”。
だからこそ、無理して完璧を目指すんじゃなくて、「崩れてもまた戻ればいいや」くらいの軽さで構えてOK。
この時期は、思考のクセを「見える化」するのがすごく有効!
たとえば1日の終わりに、
- 今日マイナスに考えたこと
- その後どう切り替えたか
…をメモしておくだけで、自分の思考のパターンがわかってきます。
第3段階「倦怠期」は意味を見失って飽きる時期
最後の壁が「倦怠期」。
思考習慣だと136日〜180日目くらいが該当します。
ここまでくると、ある程度前向きな思考もできるようになってるし、「なんとなく慣れてきたかも」って感じてるはず。
でも同時に「これって意味あるのかな…」「最近変化を感じないかも」って飽きがくるのもこの時期。
そんなときは、マンネリを打破する工夫がめちゃくちゃ大事!
・新しいノートに変えてみる
・お気に入りのポジティブな言葉を1日1つ書く
・“未来日記”を書いて、なりたい自分を具体化する
こういう小さな変化を加えるだけで、モチベも思考もリフレッシュできます。
ここを乗り越えたら、もう“思考の習慣化”はかなり定着してるはず!
次は、じゃあ実際にどうすればうまく思考を習慣化できるの?っていう実践ステップを紹介していきます。
思考の習慣化を成功させるためのステップ

まずは「5分だけ」から始めてみよう
思考の習慣化って、いきなり「今日からポジティブに生きる!」みたいに決意しても、なかなか続かないですよね。
だからこそ大事なのが、「とにかくハードルを下げること」。
たとえばこんな感じで始めてみて👇
- 寝る前に「今日よかったこと」を1つ思い出す
- 通勤中に「昨日よりよくできたこと」を考える
- 朝起きたときに「今日楽しみなこと」を1個言ってみる
どれも1〜5分でできますね。
ポイントは、“思考を動かす行動”を日常の中にちょこっと差し込むこと。
これだけで、だんだん脳が「考え方を変えるモード」に切り替わっていきます。
やる気がなくてもやる“例外ルール”が大切
「今日は疲れたし、もういいや…」ってなる日、絶対ありますよね。
そういうときのために、“やらなかった日の代替プラン”を決めておくのがオススメ!
たとえば、
- 本当は日記に5行書く→疲れてる日は「1行だけOK」
- 本当はポジティブな言葉を3つ言う→今日は「ひとことだけOK」
こういう“例外ルール”を用意しておくと、サボってる罪悪感がなくなるし、何より「続ける」っていう成功体験が積み上がるの。
それだけでもう、十分“習慣化”の道を歩いてるってことになります!
習慣化アプリや仲間の力を借りるのもアリ
1人で続けるのが苦手…って人には、習慣化をサポートしてくれるツールやアプリもすごくおすすめ!
- タスク管理アプリ(Notion、Trelloなど)
- 習慣トラッカー(日々の達成チェック)
- SNSでの「#習慣化チャレンジ」投稿
…など、モチベを保つ仕組みをいろいろ取り入れてみてください。
習慣化って、最初は地味だけど、気づけば自分の中に“当たり前”として根づいていきます。
次は、そんな習慣化をもっと確実にするために、「失敗しないための3つのルール」を紹介します。
失敗しないために守りたい3つのルール

スモールステップで達成感を積み重ねる
思考の習慣化って、「やってるつもりなのに変わってる感じがしない…」って思いがち。
でも、いきなり“劇的な変化”を求めないのがポイント。
むしろ、「え、それだけでいいの?」って思うくらいの小さなステップでOK!
たとえば、
- 朝起きて「今日もやってみよ〜」って思う
- 寝る前に「よかったことを1つ思い出す」
…こんな小さな積み重ねこそが、思考の習慣化にはめちゃくちゃ効いてきます。
「やれた自分」を毎日ちょっとずつ褒めて、自己肯定感も一緒に育てていきましょう。
「2日連続サボらない」が最大のコツ
習慣化の途中で1日サボるのって、ぶっちゃけ全然OK!
だけど、「2日連続でサボる」のは習慣のリズムを壊す最大の原因です。
人間って、1日空けると「まぁいっか」ってなる生き物だから。
だからこそ、次の日は意地でも戻る!これだけは守ってください。
もし体調が悪いとか気分が上がらない日でも、「ちょっとだけやるルール」を自分にプレゼント。
たとえば、
- 書けなかったら声に出して思い出すだけ
- 時間がなければ1分だけスマホメモに書く
…みたいな“ゆる継続”でもOK!
毎日できたらしっかり自分を褒めよう
習慣化でいちばん大事なのは、意外と「褒めること」。
真面目な人ほど、「まだまだだな…」「こんなんじゃダメだ」って思いがちなんだけど、続けるには“いい気分”で終わることがめちゃくちゃ大事!
「やった!」って気持ちが残れば、それだけで明日もまたやりたくなります。
“続けた自分”をちゃんと認めてあげることで、習慣ってどんどん根づいていきます。
まとめ
今回の記事では、思考の習慣化に必要な期間とその乗り越え方についてお届けしました。要点を以下にまとめます。
- 習慣化の平均期間は66日。ただし思考の習慣化は約6ヶ月かかる
- 習慣化には「反発期」「不安定期」「倦怠期」の3段階がある
- 小さな行動(1日5分)から始めることが成功のカギ
- サボってもOK!「2日連続でやめない」が重要
- 習慣化アプリや仲間のサポートも活用しよう
思考を変えるには、時間も根気も必要。
でも、小さな“できた”を積み重ねていくことで、確実に自分の中に新しい習慣が根づいていきます。
焦らず、比べず、自分のペースでOK。
今日から、たった5分の「思考のルーティン」、始めてみませんか?